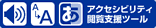3.募集活動・社内支援の準備 (4)採用決定後の取組(労働条件、職務内容、社内支援担当者)
Q 採用決定後、社内で行うことについて教えてください(労働条件、職務内容、社内支援担当者)。
A 採用した障害者の希望や障害特性と配慮事項などを踏まえ、本人に合った労働条件等を整理し、労働条件通知書等を交付します。また、採用する障害者に合わせた社内支援の担当者を決めます。
障害特性と配慮事項の社内共有
面接などで本人や家族、支援機関から収集した障害特性や配慮事項、本人の希望などの情報を社内で共有します。ただし、社内で共有する内容や範囲(職場全体または配属部署のみなど)については、面接時や採用決定時において本人の同意のもとに確認しておくことが必要です。
労働条件の整理(労働条件通知書の提示)
本人の希望、障害特性や配慮事項などにより、時差出勤を含む就業時間、通院に配慮した休日、職種や職位に応じた賃金、職務内容などにおいて、求人票に記載されていた労働条件を変更することが必要な場合もありますので、改めて整理した上で「労働条件通知書」を作成し、採用する障害者に交付します。
職務内容の選定
本人の障害特性や専門知識・技能等の習得状況(学校や職業訓練校での経験を含む)、本人の希望・意欲などを踏まえ、本人に合った職務内容を選定します(予定していた職務内容の変更を含む)。
職務内容の選定に当たっては、本人が力を発揮できる職務や専門知識・技能等を持っている人は、それらを活かせる職務を取り入れること、さらには本人が自身の目標を設定し、見通しを持って仕事に従事できるような内容も取り入れて選定することが本人の安心感や意欲の向上につながります。
また、障害者が従事しやすいように、支援機器の活用、工程の改善・環境整備などを行い、従事できる職務の幅を広げることにつなげることも大事です。
職務の幅を広げるための配慮(例)
- 作業上の配慮:手順書の見直し、支援機器の活用など
- 身体的負担の軽減:設備改善、休憩室の確保など
- 理解や判断力に関する配慮:わかりやすい説明、判断基準の明確化など
- 仕事における役割の設定:作業工程の一部を担う、補助的に行うといった役割の設定など
仕事における役割の選定例
事務職における電話応対
最初は電話の取次ぎのみの役割とし、段階的に電話応対の役割の幅を広げる。
売り場などでお客様と接する場面での仕事
お客様に声をかけられたら他の社員につなぐという役割から始める。
また、他の社員と一緒の場面で作業する、あるいは他の社員の目の届く範囲で作業するなどの環境設定を行う。
※ただし、人と話したり、接することに大きなストレスを感じる場合は、電話応対や人と接する売り場での仕事ではなく、本人が力を発揮できる他の仕事に従事できるように配慮することが望まれます。
社内において支援等を行う担当者の選定
社内において支援を行う際には、本人の職務内容や配慮事項などに合わせ、以下のような担当者(現場の上司や同僚、人事課等)を決めておくとよいでしょう。
- 本人に作業を教える人、作業において指示を出す人
- 本人から作業終了の報告を受ける人、質問を受ける人
- 本人と作業のふり返りを行う人、労働条件面について相談する人、体調面や健康面について相談する人
- 支援機関と相談する人
- その他本人のために必要な介助などを行う人 など
なお、全ての担当者を決める必要はなく、また、一人の社員の担当が重複することや一つの役割の担当者が複数人となってもよいですが、一部の社員にだけ負担のかからないようにすることが必要です。
また、これらの担当者とその役割については、必ず本人に伝えることが必要です。
※障害者雇用の義務の対象となる事業主においては、「障害者雇用推進者」を選任するように努めることが必要になります。
(障害者雇用推進者の業務)
障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備、障害者雇用状況の報告、障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出など
社内における支援体制の強化のために
障害者職業生活相談員の配置
障害者の雇用の促進等に関する法律では障害者を5人以上雇用している事業所は障害者職業生活相談員を選任し、障害者の職業生活全般の相談、指導を行わせることとなっています。各都道府県で開催している「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講し修了することなどにより資格を得ることができます。
企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置
企業在籍型職場適応援助者とは、企業に在籍し、同じ企業に雇用されている障害のある労働者の職場適応に向けた支援を行う支援者です。企業在籍型職場適応援助者ならではの支援の強みとして、同じ企業内で支援が行われることから、課題の早期把握とタイムリーで切れ目のない支援が可能であることや、障害者社員の受入準備から職場定着に至るまでの一貫した支援が可能であることなどが挙げられます。 企業在籍型職場適応援助者として支援を行うためには、企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講し修了する必要があります。
※職場適応援助者は、支援の場においては「ジョブコーチ」と呼ばれます。
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金を活用した介助者等の配置
- 障害者介助等助成金
職場介助者の配置または委嘱助成金(重度視覚障害者、重度四肢機能障害者などが対象)、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金(6級以上の聴覚障害者が対象)などがあります。
- 職場適応援助者助成金
企業在籍型職場適応援助者による支援を実施した事業主に対しては、助成金(職場適応援助者助成金)が支給されます。
- 重度障害者等通勤対策助成金
通勤用バス運転従事者の委嘱助成金や通勤援助者の委嘱助成金(重度身体障害者、知的障害者、精神障害者などが対象)などがあります。
これらの助成金は企業からの申請に基づき予算の範囲で支給決定されるものです。支給要件や支給額、支給期間または支給回数の限度がありますので、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)と相談することが必要です。
※精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
全国の都道府県労働局において、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座を行っています。
※企業の皆様を対象とした障害者雇用支援に関するセミナーなど
そのほか、自治体や支援機関において、企業の皆様を対象とした障害者雇用支援に関するセミナーなどの研修(企業単位または複数の企業を参集)を実施していますので、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に問い合わせるとよいでしょう。