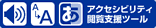2.採用計画の検討・採用の準備 (1)障害者雇用の計画(採用計画)
Q 障害者の採用計画は、どのように考えたらいいですか?
A 社内の状況を分析し、障害者雇用の目的を明確にした上で具体的に採用計画を検討し、社内の共通認識を得た上で進めることが必要です。
障害者雇用の目的
目的の例1:障害者の働く場を提供する
・企業としての社会的責任、社会貢献のために障害者の働く場を提供する。
・支援機関から、障害者でも働けるのではないかと勧められ、障害者雇用を行う。
・多様な人材を雇入れ、多様な人材と共に働く社員の意識の向上を図り、組織の活性化につなげるため、障害者雇用を行う。
すでに法定雇用率を達成している場合や障害者雇用の義務の対象範囲外(労働者40.0人未満)の場合であっても、企業としての方針を明確にし、社内で共通認識を図りながら、積極的に障害者雇用を進めていくことが必要です。
障害者雇用のメリットを十分に理解しながら、企業の状況に応じて雇用できる人数を決定します。
なお、障害者の働く機会を幅広く増やしていくという観点から、障害者手帳を所持していない発達障害者や高次脳機能障害者、難病のある人などの雇用についても、幅広く検討することが望まれます。
目的の例2:法定雇用率の達成を目指す
○障害者雇用率が法定雇用率を下回っており、ハローワークから指導を受けているため、雇用率達成を目指す。
法定雇用率未達成の状況にあり、雇用率達成のために企業として取り組んでいかなければならないことを経営者として理解し、社内にも周知しながら、企業全体で可能な限り早急に取り組むことが必要です。
①企業において障害がある人がいるかどうかを把握・確認します。
②企業で把握した障害者の数と法定雇用率における不足数を勘案し、法定雇用率を達成するために必要な採用数を決定します。
※障害者雇用の実現にあたっては、障害者雇用のメリットを十分に理解し、上記の目的の例1のことも加えて検討することが大事です。
採用計画の検討のポイント
障害者雇用の目的を踏まえ、採用計画の具体的な検討を行います。
採用人数
企業における障害者雇用数や障害者雇用率の状況などを踏まえて、採用人数を決めます。
採用の時期
基本的には、次のいずれかの時期に設定できるように検討します。
①企業の障害者雇用率が未達成または欠員補充を障害者雇用で考える場合は、できるだけ早い時期に設定する。
②企業における年度の採用計画に沿った時期に設定する。
③学校や職業能力開発校などの卒業(修了)時期に合わせた時期に設定する。
④そのほか企業の事情に応じて随時設定する。
職務内容
採用を予定する部署及び職務内容について検討します。
労働条件(雇用形態、勤務時間、休日・休暇、賃金等)
雇用形態や賃金は、職務内容や責任の範囲、就業時間などを踏まえて検討します。
なお、採用計画の検討にあたっては、配慮により能力を発揮できる障害者もいるという観点から、職務内容や就業時間などは柔軟に検討することが必要です。(例えば求人票には「職務内容や就業時間、休日などは相談に応じます」と記載するなど)
社内支援体制の整備や支援機関との連携等の検討
社内支援体制の整備
採用や採用後の支援のことを見据えて、採用の担当者(人事課など)の役割や配属部署の担当者の役割を整理します。
支援機関との連携、活用する支援制度等
採用後の職場定着のために活用できる障害者トライアル雇用やジョブコーチ支援などの支援制度、各種助成金制度について情報収集します。
これらの検討を行う場合は、社内において、経営者、人事課、配属部署の担当者などで十分に打ち合わせを行い、採用計画の内容を社内に伝えることが大事です。
障害者雇用を進めていくにあたって不安などがある場合は、ハローワークや地域障害者職業センターをはじめとする支援機関から支援を受けるとよいでしょう。